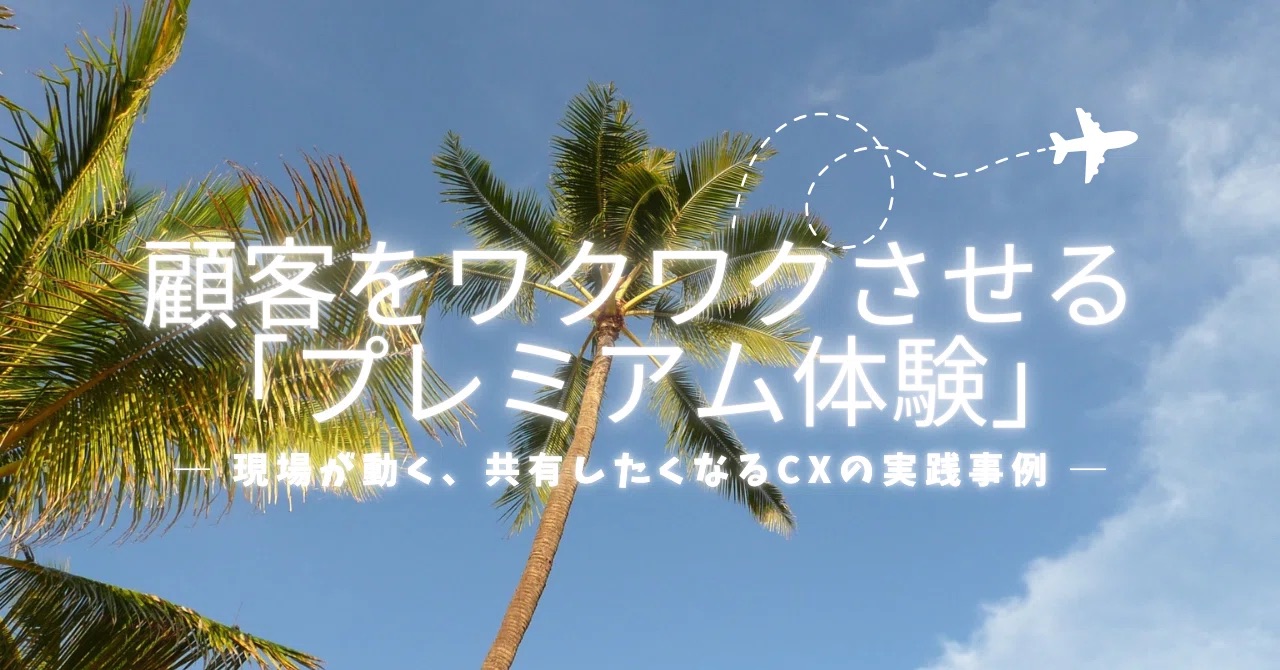2022.12.15
サービスサイエンス
コロナ禍でのちょい飲み戦略

コロナ禍で大きく飲み屋さんの形態も変わってきています。
これまでは、居酒屋さんのようにある程度落ち着いて座って、ゆっくり飲みながら食べる形がありました。勿論、しっかりとした食べ物メインのお店も多くありました。
私も週に3,4回は会食と称して利用させていただいておりました。ところが、コロナ禍の影響で回数もめっきり減っています。
「ちょい飲み」や「招待制・会員限定」サービスが増えてきている
コロナ禍前から、ファストフードなど外食チェーンの店舗内で、夕方から酒とつまみを販売する**「ちょい飲み」サービス**が広がっていました。
以前話題になった**日本ケンタッキー・フライド・チキン(KFC)**が、東京・高田馬場でビールやワインなどの酒を楽しめる新業態店舗を始めていました。昼間は通常のメニューに加え、こだわりのコーヒーやスイーツなどを提供し、午後5時からはアルコールを提供。国内外から取りそろえた地ビールやワインのほか、サントリー酒類と共同開発したハイボール「カーネルハイ」など約40種類のアルコール類を用意しており、得意とする鶏肉を使った料理やサラダなど酒に合うメニューも取りそろえていました。残念ながら、現在はアルコールの提供はされていないようで、ロッカー式の宅配代行受け取り口などを設置してリニューアルオープンしているとのことです。
また、コーヒーチェーン大手、スターバックスコーヒージャパンは東京・丸の内に食事や酒などを提供する店舗を19年3月30日に開店しました。牛丼チェーン「吉野家」やラーメンチェーン「日高屋」といった先行組は、低価格でお酒が楽しめるとあって、サラリーマンを中心に人気は高いようです。現在は全国9店舗で実施されています。
飲食の業態としても簡単なおつまみとお酒で、帰りがけにちょっと飲んで帰る「ちょい飲み」業態も増えています。コロナ禍の影響で長居を嫌うユーザー心理の反映ではないでしょうか。
また、逆にコロナ禍対策もしっかりとして不特定多数を対象にせずに、招待制や会員制にして、特別感のあるサービスを提供するお店も増えてきました。
これらは、昔からあった業態でしたが、コロナ禍で進化しており、SNSなどの集客拡散システムを上手く利用することにより、客単価をあまりあげずに満席を常にキープする事で継続営業ができています。
ここで、「ちょい飲み」を戦略的に考えてみると
アメリカの経営学者で「経営戦略の父」として名高いイゴール・アンゾフが立案し、事業拡大マトリクス経営戦略を検討する著名なフレームワークの一つに**「アンゾフの事業拡大マトリクス」があります。事業の拡大の方向性を「製品軸」と「市場軸」**に分けて、どの方向性で成長していくかの意思決定に使うとともに方向性を意識した施策を立案するためのフレームワークとして使用します。
このフレームワークに従いファストフードの成長ベクトルを考えると、ケンタッキーの今回の戦略は、新製品の提供になりますが、市場(顧客)はどちらをメインで狙っているのでしょうか?
おそらく**既存顧客(A)**なんでしょうね。しかし、既存顧客(A)であれば、プロントとか同じような形態の競合が多く存在し、劇的な成長路線を描くことが困難なように思えます。
ここはひとつ、新規顧客(B)しかも、銀だこのように立呑ができ、チキンとクラフトビールなどでサクッと飲めるお店などはどうでしょうか?
バイイングパワーと独自のエキスを利用したケンタッキー焼き鳥メニューをホッピーのセットで格安で提供する、なんてどうでしょう?話題性もあり、ワールドビジネスサテライトに取り上げられるかもしれませんよ。それくらいの差別化とリスクを負わないと、この激戦業界で成長は厳しいような気がします。そこでヒントを以下の書きます。
顧客体験的な観点から見ると
飲食事業での調査結果をみると、推奨者は「美味しい」「リーズナブル」「清潔さ」などのコメントは殆ど出てきません。飲食店に求めてきていることは「味」「価格」「清潔」などは、必要条件であって、十分条件にはなっていません。
今の顧客が飲食店に望んでいるのは、従業員さんの人的なコミュニケーションやスタッフの元気さであったりします。調査結果のコメントなどには、「スタッフが元気でこっちも元気になりました」や「気にかけてくれて、嬉しかった」などが目立つようになります。
コロナ禍で外食の機会が減っている中、やはり人的なコミュニケーションを介して、元気にさせてくれるお店が流行る気がします。
ポイントは現場の元気です。
スタッフが作業ベースの仕事をこなしている飲食店は、勿論空腹を満たすためには必要ですが、元気をもらえる場にはなりません。
そこで当社では現場スタッフが元気になるための、「FACT based Training 」という顧客調査と研修をセットにして成果が出せるモデルを、これまでの企業様と開発しました。
是非、詳細はこちらのURLをご覧になってください。
https://total-engagement.jp/information/2252/
顧客体験(CX)、NPSに
関するご相談
トータルエンゲージメントグループでは、これまで延べ100社以上15,000店舗以上のアパレル・小売流通・飲食宿泊から金融、行政などB2C事業からSaaSやメーカーのようなB2B事業など、様々な業種での支援実績がございます。
CXにおける改善をツール提供だけでなく、全体の戦略をもとに策定・実施まで一気通貫でサポートいたします。まずは無料相談からお気軽にお問い合わせください!
メルマガ登録
Total Engagement Groupの最新ニュースや、CX・NPSの最新トレンドを
メールマガジンにて配信しております。ご登録はこちらから!
人気記事
カテゴリー
タグ
- AI
- B2B
- B2Bセールス
- B2Bマーケティング
- CJM
- CRM
- CX
- eNPS
- EX
- NPS
- SNSマーケティング
- アンケート
- イベント
- エンゲージメント
- サステイナブル
- サービス
- サービス・プロフィット・チェーン
- サービス品質
- スタートアップ
- スポーツ
- セールス
- ディズニーランド
- バイヤージャーニーマップ
- ファンマーケティング
- フィードバック
- ブランディング
- プレミアム
- ホスピタリティ
- マネジャー
- マーケティング
- リーダーシップ
- レジ
- ロイヤルティ
- ロイヤルティプログラム
- ワークライフバランス
- 万博
- 人材不足
- 仕組み化
- 企業文化
- 企業研修
- 体験価値
- 価値提供
- 共感
- 店長研修
- 店頭
- 従業員体験
- 従業員満足
- 感情労働
- 採用活動
- 推し活
- 支払方法
- 改善活動
- 福利厚生
- 経営
- 自治体
- 行列
- 講演
- 顧客体験
- 顧客満足
- 顧客理解
- 顧客調査