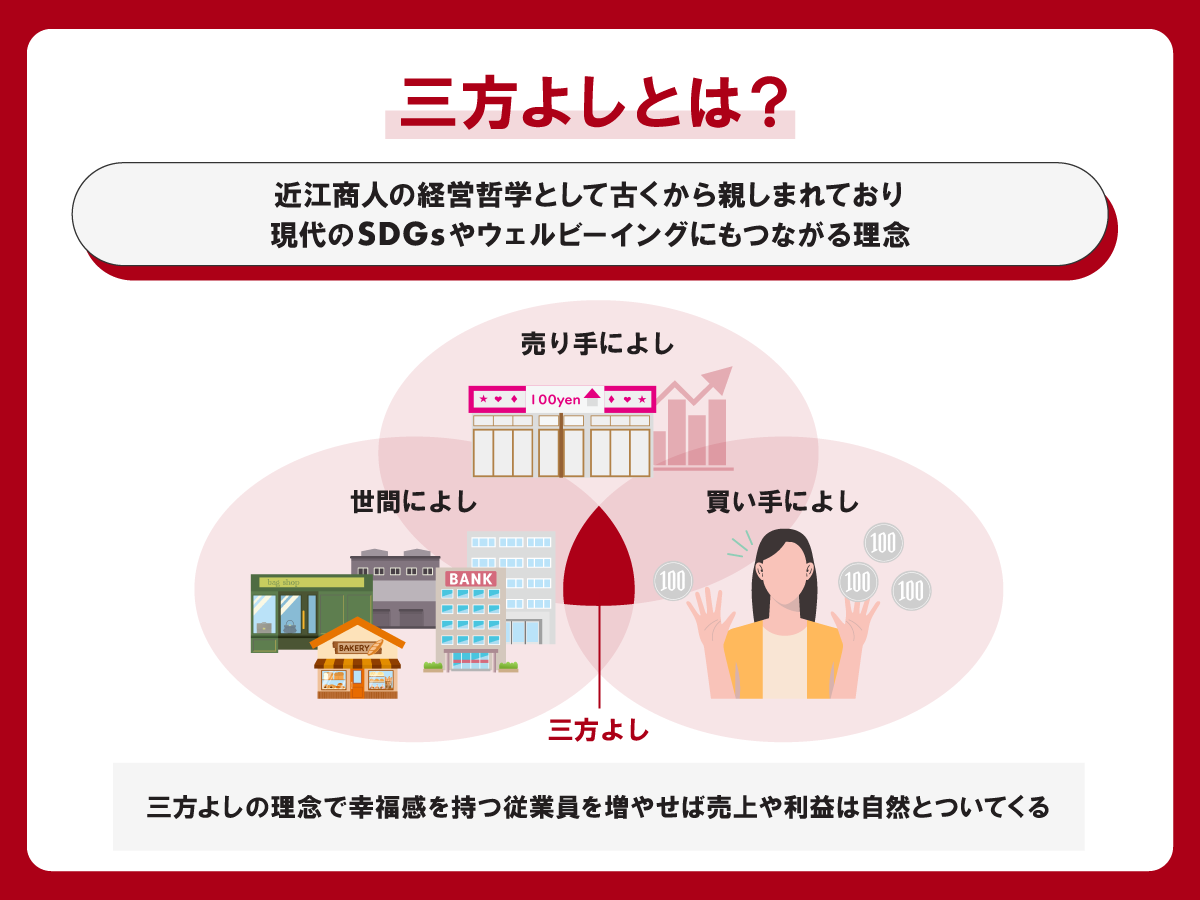2025.07.06
NPS
NPSスコアが高い理由とその影響を徹底解説

NPS(ネットプロモータースコア)は、NPSスコアを通じて企業が顧客の満足度を測定するための指標として広く利用されています。このコラムでは、NPSスコアが高い理由とその高いスコアがもたらす影響について徹底解説します。
NPSは顧客満足度や従業員エンゲージメントとどのように関連しているのか、また日本企業におけるNPSの現状と課題についても詳しく掘り下げます。NPSスコアを高くするための改善ポイントや具体的な施策について学ぶことで、御社の顧客満足度を高め、業績向上につなげるヒントを得ることができるでしょう。
さらに、主要なNPSツールの特徴や導入事例を比較し、NPSに最適なソリューションを見つけるための情報を提供します。NPSに関するよくある質問にもお答えし、最新情報やコラムを通じて、NPSの理解を深めるお手伝いをいたします。この記事を通じて、NPSスコアを高く保つための知識を身につけ、高い顧客との信頼関係を強化し、ビジネスの成長をサポートします。
目次
NPSとは?顧客満足度指標の全体像と高スコアを実現する方法
NPS(ネットプロモータースコア)は、企業が顧客のブランドやサービスに対する忠誠心を測定するために使用する重要な指標です。顧客満足度調査との違いは、NPSが顧客が企業を他の人に推薦する可能性を評価する点にあります。これにより、企業は顧客のロイヤルティを数値化し、事業の成長に結びつけることができます。
NPSの計算方法は、推奨者の割合から批判者の割合を引くことで求められ、一般的にスコアが高いほど顧客の支持が強いことを示します。低いNPSスコアの場合、企業は顧客からのフィードバックを積極的に取り入れ、サービスの質を向上させることが求められます。
さらに、顧客との接点を増やし、パーソナライズされた体験を提供することも重要です。これにより、顧客はブランドに対して強い愛着を持ち、NPSの向上につながります。
NPSの基礎知識:定義と計算方法
NPSの基本概念とその意味
NPS(ネット・プロモーター・スコア)は、顧客が企業や製品を他者に推奨する可能性を測定するための指標で、顧客満足度(CS)を評価する手法として広く用いられています。企業にとっては、顧客との接点を通じて得られるフィードバックを基に、顧客関係を評価する重要なツールとなります。
NPSスコアは、顧客が企業をどれほど推奨したいかを数値化し、その顧客基盤の強度や将来の成長性を評価するための指標です。計算方法としては、顧客を推奨者、批判者、中立者の三つのカテゴリに分類し、推奨者の割合から批判者の割合を差し引くことで求められます。
NPSの値が低い場合、企業は顧客に価値を提供できていない可能性があり、改善のための戦略的インサイトを得ることができます。NPSの理解は、企業が顧客中心の戦略を立案し、顧客の声を反映させることで持続的な成長を促進する上で非常に重要です。
計算方法と調査手順(推奨者-批判者の差による算出)
企業が顧客満足度を向上させるために利用する指標の一つにNPS(Net Promoter Score)があります。このNPSの計算方法は非常にシンプルで、推奨者の割合から批判者の割合を引くことで算出されます。具体的には、顧客に「この製品やサービスを他の人に推薦しますか?」と尋ね、0から10までのスコアを付けてもらいます。9または10のスコアを付けた顧客は推奨者とされ、0から6のスコアを付けた顧客は批判者と分類されます。7または8を付けた顧客は中立者とみなされ、NPSの計算には含まれません。
NPSの調査手順は、まず顧客アンケートを実施し、スコアを集計することから始まります。企業はこのデータをもとに、顧客満足度の違いを分析し、NPSが低い要因を特定することができます。これにより、企業は具体的な改善策を導き出し、顧客満足度を高める戦略を策定することが可能です。定期的なNPS調査は、顧客の声を直接反映し、企業が継続的に顧客との関係を深化させるための重要な手段です。
NPSと顧客満足度・従業員エンゲージメント指標の違い
NPSと顧客満足度の相関および相違点
企業が顧客のフィードバックを評価する際、NPS(ネットプロモータースコア)と顧客満足度(CSAT)は重要な指標となりますが、それぞれ異なる側面に焦点を当てています。NPSは主に顧客のロイヤルティを示すスコアとして、将来的な成長の指標として役立ちます。
具体的には、「あなたはこの商品やサービスを他者にどの程度勧めたいと思いますか?」というシンプルな質問を通じて、その推奨意向を数値化します。計算方法は、推奨者の割合から批判者の割合を引くことで得られます。一方で、顧客満足度は商品やサービスが顧客の期待にどの程度応えているかを測るもので、複数の質問を用いて具体的な満足度を評価します。
多くの企業はこれらの指標を相互に関連付けて分析しますが、顧客満足度が高い場合でもNPSが低いことがあります。例えば、顧客が製品に満足していても、他者に推奨するほどの熱意を持たないことが原因です。このように、両者の違いを理解することが、企業が包括的な顧客戦略を策定し、実際の顧客体験を改善する上で不可欠です。
NPSとeNPS(従業員向け指標)の比較
NPS(ネット・プロモーター・スコア)は、企業が顧客満足度を評価するために広く利用される指標です。一方で、eNPS(エンゲージメント・ネット・プロモーター・スコア)は、従業員の満足度やエンゲージメントを測定するためのものです。
この2つの指標は、どちらも「推奨者」の割合をベースにした計算方法を用いる点で共通していますが、ターゲットが異なるため、その目的や適用方法に違いがあります。
\n\nNPSは、顧客のロイヤルティを高めるための施策を考える際に役立ちます。一方でeNPSは、従業員の職場環境や組織文化の改善に焦点を当てており、あなたの企業の内部からの強化を目指します。
これにより、従業員のモチベーションが高まると同時に、結果として顧客満足度の向上にもつながります。\n\n企業が市場での競争力を維持し、耐久性のあるビジネスモデルを構築するためには、顧客と従業員の両方の観点を考慮に入れたアプローチが必要です。
これにより、低い満足度を早期に察知し、適切な対策を講じることが可能になります。両者の違いを理解し、効果的に活用することで、企業は持続的な成長を実現できるでしょう。
日本企業におけるNPSの現状と課題
業績向上との直接的な結びつきが見えにくい理由
当社は2010年よりNPS(ネット・プロモーター・スコア)を国内企業に提案をしてきました。最近は多くの企業で、NPSは顧客のロイヤルティを測るための指標として多くの企業で利用されています。
しかし、業績向上との直接的な関連性が見えにくいとされています。これは、NPSが顧客の意図や感情を反映するスコアである一方で、売上や利益といった具体的な業績指標と直結しにくいことが一因です。
たとえば、NPSが高い場合でも、顧客が実際にどの程度購入につながるかは、他の多くの要因に影響されます。さらに、NPSは特定の時点での顧客の感想を集めるため、長期的な業績の変動を捉えることが難しいです。
また、NPSは個々の顧客体験に基づいているため、会社全体の業績を俯瞰するには限界があります。
企業がNPSを活用して業績を向上させるには、他の指標やデータと組み合わせ、総合的に分析することが重要です。これによって、NPSの数値が持つ意味合いをより具体的に理解し、業績向上のための具体的なアクションを導き出すことが可能となるでしょう。
平均スコアが低い背景:文化的傾向と評価基準の違い
企業が顧客満足度を測るために利用するNPS(ネットプロモータースコア)は、その計算方法を通じて顧客の忠誠度を数値化します。しかし、日本の企業においては、このスコアが低いという違いがしばしば見られます。
この現象の背後には、日本特有の文化的傾向と評価基準の違いがあります。日本の文化では、謙虚さや調和を重視し、顧客が高評価を与えることを控える傾向があります。また、日本では品質やサービスの評価基準が欧米と異なり、結果的にNPSが低く算出されることも少なくありません。
さらに、回答者が中立的な選択を好み、極端なスコアを避ける傾向も影響しています。これらの文化的要因がNPSの結果に直接影響を与え、国際的な比較を複雑にしています。
したがって、企業はNPSを活用する際に、これらの文化的背景を理解し、戦略に組み込むことが重要です。
回答傾向と代替指標の検討
企業の成長にとって重要な要素である顧客満足度を測定する指標として、NPS(ネット・プロモーター・スコア)が広く利用されています。
しかし、NPSの計算方法は、回答者の傾向や文化的背景の違いにより、すべての企業にとって最適な指標となるわけではありません。特に、日本企業においては、NPSの値が低く出ることが多く、これは文化的な要因や評価基準の違いによるものです。このため、NPSの結果だけに依存せず、他の代替指標の併用が推奨されます。例えば、CSAT(顧客満足度スコア)やCES(顧客努力スコア)などを活用することで、顧客満足度を多角的に把握し、具体的な改善策を導き出すことが可能です。
これにより、企業は顧客のニーズを正確に理解し、サービスの質を向上させるための適切な施策を講じることができます。さらに、定期的に調査を行い、トレンドを把握することで、市場の変化に応じた柔軟な戦略の採用が求められます。
NPSの推移確認と比較の有用性
企業はNPS(Net Promoter Score)の推移を定期的に確認し、他社や過去の自社データと比較することで、製品やサービスに対する顧客満足度の違いを明確に把握できます。
このプロセスは、企業の顧客ロイヤルティの状態を理解し、戦略的な改善を行うために不可欠です。NPSの計算方法を適切に運用し、その推移を追うことで、顧客の声に基づいた迅速な対応が可能になり、トレンドの変化を早期に察知することができます。業界全体のベンチマークを活用することで、競合他社と比較して自社の位置付けを理解し、自社の耐久性や弱みを客観的に評価できます。
さらに、NPSの変化を分析することで、製品やサービスの改善点を明確にし、低い顧客満足度を向上させるための実行可能な施策を立案できます。
これにより、企業は継続的な成長と顧客との信頼関係を築くことが可能となります。
NPS向上のための改善ポイント
影響要因の特定と調査手法の使い分け
企業が顧客満足度を向上させるためには、NPS(ネット・プロモーター・スコア)の低い要因を特定し、適切な調査手法を活用することが不可欠です。顧客のフィードバックを詳細に分析して、製品の品質、カスタマーサービス、価格設定といった要素がNPSにどのような影響を与えているのかを計算方法を用いて明らかにすることが重要です。
これらの要因を示すことで、具体的な改善策を講じる基盤が整います。リレーショナル調査とトランザクショナル調査を使い分けることが特に有効です。リレーショナル調査は企業と顧客の全体的な関係性を評価するのに適しており、長期的な戦略構築に役立ちます。一方で、トランザクショナル調査は特定の購入またはサービスの経験後における顧客満足度を測定するため、迅速なフィードバックが必要な場合に最適です。
これにより、企業は顧客のニーズに迅速かつ的確に対応することが可能となり、結果としてNPSの向上につながります。
リレーショナル調査とトランザクショナル調査の適切な運用
企業にとって、ブランドの価値を高め、顧客満足度を向上させるためには、リレーショナル調査とトランザクショナル調査の違いを理解し、適切に運用することが不可欠です。リレーショナル調査は、概念的に企業と顧客の長期的な関係性を評価するもので、定期的に実施することで顧客満足度の変化を計算することができます。この調査は、顧客のロイヤルティを測る指標としても有効であり、一般に顧客満足度が低い傾向にある場合でも、その原因を明らかにする手助けとなります。
一方で、トランザクショナル調査は、特定の取引後の顧客の直近のフィードバックを収集することに特化しており、顧客体験の質を直接的に評価するために用いられます。これにより、企業は迅速に問題を特定し、必要な改善策を講じることが可能です。
両者の調査を組み合わせることにより、企業は顧客の声を多角的に捉えることができ、結果としてブランド価値の向上や顧客満足度の向上に繋げることができます。調査結果を部門横断的に共有し、組織全体で活用することが、持続的な成長の鍵となります。
社内共有とフィードバックによる組織的改善
企業内でのNPS(ネット・プロモーター・スコア)を活用した改善は、顧客満足度の向上に直結します。
NPSは顧客が企業を他者に推薦する可能性を数値化したもので、その計算方法を社員全員が理解し、低い数値に対する具体的な改善策を講じることが重要です。社内でフィードバックを自由に共有することで、顧客の声を全社員が把握し、組織全体で迅速かつ効果的な対応が可能となります。これにより、顧客満足度の違いを生み出し、企業全体のNPSを改善することができます。
さらに、フィードバックの透明性を高め、改善提案のプロセスに全社員が参加できる環境を整えることで、従業員のエンゲージメントを向上させ、組織の一体感を強化します。このような取り組みが、持続可能な企業成長の基盤を築くのです。
アンケート設計とデータ分析による具体的施策
アンケート設計とデータ分析を活用した具体的施策では、まずは企業にとって重要な顧客満足度の向上を目指し、NPS(ネットプロモータースコア)の精度を高める質問の設計が不可欠です。
これには、顧客の体験や期待を的確に捉えるために、明確で回答しやすい質問形式が求められます。オープンエンド質問とクローズドエンド質問を組み合わせることで、質的および量的データのバランスが取れた情報を得ることができ、企業のNPSが低い場合の要因分析に役立ちます。収集したデータは、顧客の声を深く理解し、企業と顧客の違いを把握するために活用されます。
続いて、データ分析では、NPSスコアの変動要因を特定するために、統計的手法を駆使してパターンやトレンドを明らかにし、特定の顧客セグメントやタッチポイントに対する改善策を策定します。さらに、データの可視化を行うことで、関係者間での情報共有が促進され、具体的なアクションプランの策定が支援されます。
施策の実施後には、その効果を定期的に評価し、フィードバックを基に継続的な改善を図ることが求められます。
これらのプロセスを通じて、企業は持続可能な顧客満足度の向上を実現し、NPSの計算方法に基づく評価を通じて、顧客との良好な関係を築くことができます。
NPSツールとソリューションのご紹介
主要なNPSツールの特徴と比較
NPS(ネット・プロモーター・スコア)は、顧客満足度とロイヤルティを評価するための重要な指標として、さまざまな企業で取り入れられています。
このコンテンツでは、主要なNPSツールについてその特徴と違いを詳しく見ていきます。SurveyMonkeyは、直感的なインターフェースと豊富なテンプレートを提供し、幅広い企業で利用されています。特に中小企業におけるNPSの計算方法の精度向上に貢献しています。Qualtricsは、データ分析機能が高度でカスタマイズの自由度が高く、データ駆動型の企業に支持されています。Medalliaは、リアルタイムでの顧客フィードバック収集と迅速なインサイト提供を特徴とし、顧客満足度を低い状態から改善するための強力なツールです。Zendeskは、顧客サポート機能と統合されたNPS機能を持っており、サポートチームの効率を向上させるとともに、CS(カスタマーサポート)の向上に寄与します。
各ツールには固有の強みがあり、企業の製品やサービスに最適なものを選定することが、顧客満足度の向上に繋がります。
導入事例と活用ポイント(企業固有名詞は一般名称に置換)
様々な企業が顧客満足度の向上とビジネス成果の改善を目指して、NPS(ネットプロモータースコア)を採用しています。
例えば、ある製造業の企業では、NPSを導入することで、海外の顧客からのフィードバックを効率的に収集し、製品改善に役立てています。一方、サービス業の一般的な企業では、NPSスコアの分析を通じて顧客のニーズを詳細に把握し、サービスをパーソナライズすることで、リピーターの増加を実現しました。
これらの事例が示すように、NPSは単なる顧客満足度の指標にとどまらず、戦略的な顧客関係管理のツールとしても利用されています。導入にあたっては、企業の特性や市場環境に応じたカスタマイズが不可欠ですが、これを適切に実施することにより、企業は競争優位性を確立する強力な手段を得ることができます。
NPSを活用することで、企業は顧客の声をビジネス戦略に反映させ、持続的な成長を促進することが可能です。特に、他の企業と並ぶ中で、低い顧客満足度の原因を特定し、改善するための質問を通じて、顧客の期待に応えることが求められます。
NPSに関するよくある質問(FAQ)
NPSスコアの平均値はどの程度か?
NPS(ネット・プロモーター・スコア)は、企業が製品やサービスに対する顧客の推奨意欲を測定するための重要な指標です。
このスコアは、顧客満足度やロイヤルティを評価する際に広く利用されており、推奨者の割合から批判者の割合を引くことで計算されます。スコアは-100から100の範囲で示されます。NPSスコアの平均値は国や業界によって異なるものの、一般的に世界的な平均は20前後とされています。
しかし、日本では文化的背景や評価基準の違いにより、NPSスコアが他国に比べて低い傾向があります。具体的には、日本の企業におけるNPSスコアは平均して-40から+40の範囲に入ることが多いです。
これは、日本の消費者が批判的であることや、満足度を表現する際に控えめである文化が影響しています。NPSスコアは単なる数値ではなく、企業が顧客との関係を深めるために活用できる貴重な情報源です。このデータを基に、企業はサービスの改善や顧客体験の向上に取り組むことが重要です。
高いNPSスコアを推進する要因は何か?
企業が高いNPSスコアを達成するためには、顧客満足度を重視した取り組みが不可欠です。
そのためには、顧客からのフィードバックを直接受け取る接点を設け、迅速に対応する仕組みを構築することが重要です。これにより、顧客の不満を早期に解消し、忠誠心を高めることができます。企業と顧客の間に強固な信頼関係を築くには、透明性のあるコミュニケーションと一貫したサービスの提供が求められます。
さらに、従業員のエンゲージメントを高め、顧客対応の質を向上させることも重要です。従業員の意識改革を進め、顧客満足度を高める企業文化を醸成することで、高いNPSスコアの獲得につながります。
最後に、顧客データを分析して、個々のニーズに応じたカスタマイズされたサービスを提供することが、競争優位性を示す鍵となります。NPSの計算方法とその意味を正しく理解し、低いスコアが示す問題点を改善することで、企業はより高いNPSスコアを目指すことができます。
NPSを改善するためにはどのような対策が必要か?
NPS(ネット・プロモーター・スコア)を改善するための対策には、企業が顧客満足度を向上させる施策を講じることが重要です。まず、製品やサービスに対する顧客のフィードバックを詳細に分析し、満足度が低い点を特定します。
これにより、具体的な改善策を立てることが可能となります。次に、顧客体験の質を高めるために、パーソナライズされたサービスを提供することが効果的です。また、迅速で丁寧なカスタマーサポートは、顧客満足度に大きな違いを生み出す要因となります。さらに、従業員のエンゲージメントを向上させることで、顧客対応の質が向上し、NPSの向上につながることがあります。
加えて、データドリブンな方法でNPSの計算方法を理解し、戦略的な改善策を講じることも必要です。これにより、顧客との信頼関係が強化され、長期的な顧客ロイヤルティの向上につながります。
改善に要する期間についての考察
企業がNPS(ネット・プロモーター・スコア)を改善するためには、短期的な施策と長期的な戦略の両方をバランスよく実施することが重要です。
短期間での改善を目指す際には、顧客満足度向上のために、顧客からのフィードバックを迅速に分析し、即座に対応可能な問題を解決することが求められます。たとえば、顧客対応のプロセスを改善したり、製品やサービスの品質を向上させたりすることで、数ヶ月以内にNPSを向上させることが可能です。\n\n一方で、長期的な改善には、企業全体のカルチャーやビジネスモデルを顧客中心にシフトする必要があります。これには、従業員の意識改革やリーダーシップの変革が含まれ、数年にわたる継続的な取り組みが必要です。
これらの長期施策は、NPSの持続的な向上に寄与し、企業の成長を支える基盤となります。\n\n最終的に、短期および長期の施策を効果的に組み合わせることが、NPSが低い状態からの脱却を目指す上での鍵となります。これにより、企業は顧客満足度を高め、持続的な成長を遂げることができるでしょう。
調査結果の効果的な分析方法とは?
企業の製品やサービスに対する顧客満足度を高めるためには、調査結果の効果的な分析が欠かせません。特にNPSの調査結果は、データの整理と視覚化から始めることが重要です。
データを視覚的に整理することで、顧客満足度のトレンドやパターンをより明確に理解できます。次に、分析の基準を設定し、NPSスコアの計算方法に基づいて、推奨者、批判者、中立者といった異なる顧客セグメントの割合を詳しく比較検討します。この違いを把握することで、企業が直面する課題を特定し、低い満足度を引き上げるための具体的な施策を考えることが可能です。
さらに、顧客のフィードバックを深く分析するためにテキストマイニングを活用し、定量的なデータとして取り扱うことで、より精度の高い分析を実現します。
分析結果は企業全体で共有し、全員が理解しやすい形で報告することで、具体的な改善施策につなげることができます。継続的な分析プロセスの見直しと改善が、顧客満足度の向上に繋がります。
最新情報とコラム:NPS入門・実践編
NPS(ネット・プロモーター・スコア)は、顧客満足度を測るための重要な指標として、国内外の多くの企業で利用されています。本コラムでは、NPSに関する最新のトレンドや実践的なアドバイスを紹介します。まず、NPSの利点と限界を探り、企業がどのようにしてこの指標を活用して競争優位を築くことができるかを考察します。次に、最新の調査結果や統計データに基づいて、NPSの進化を分析し、業界ごとのベストプラクティスを共有します。
また、成功事例を通じて、NPSの効果的な運用方法や注意すべきポイント、顧客満足度が低い原因についても解説します。最後に、NPSを活用したマーケティング戦略や、顧客体験の向上に向けた取り組みを紹介し、実際のビジネスシーンでの応用例を提供します。これにより、企業がNPSを最大限に活用し、顧客との関係を強化する方法を理解する手助けをします。
顧客体験(CX)、NPSに
関するご相談
トータルエンゲージメントグループでは、これまで延べ100社以上15,000店舗以上のアパレル・小売流通・飲食宿泊から金融、行政などB2C事業からSaaSやメーカーのようなB2B事業など、様々な業種での支援実績がございます。
CXにおける改善をツール提供だけでなく、全体の戦略をもとに策定・実施まで一気通貫でサポートいたします。まずは無料相談からお気軽にお問い合わせください!
メルマガ登録
Total Engagement Groupの最新ニュースや、CX・NPSの最新トレンドを
メールマガジンにて配信しております。ご登録はこちらから!
人気記事
カテゴリー
タグ
- AI
- apple
- B2B
- B2Bセールス
- B2Bマーケティング
- CJM
- CPA
- CRM
- CS
- CX
- eNPS
- EX
- HR
- LTV
- MUI
- NPS
- Shop
- SNSマーケティング
- SPC
- Zappos
- おまかせ
- おもてなし
- らしさ
- アンケート
- イベント
- エンゲージメント
- カスタマーサクセス
- カルチャー
- ギフト
- クーポン
- サステイナブル
- サポートセンター
- サービス
- サービス・プロフィット・チェーン
- サービス品質
- スタッフ対応
- スタートアップ
- スターバックス
- スポーツ
- セールス
- タッチポイント
- ディズニーランド
- バイヤージャーニーマップ
- パーパス
- ファン
- ファンマーケティング
- フィードバック
- ブランディング
- プレミアム
- ホスピタリティ
- ホテル日航成田
- マネジャー
- マーケティング
- リーダーシップ
- レジ
- ロイヤルティ
- ロイヤルティプログラム
- ワークライフバランス
- 万博
- 三方良し
- 中小企業
- 人材不足
- 人的資本
- 仕組み化
- 企業文化
- 企業研修
- 体験価値
- 価値提供
- 共感
- 厚利少売
- 地域再生
- 店長研修
- 店頭
- 従業員体験
- 従業員満足
- 心理的安全性
- 感動体験
- 感情労働
- 技術
- 投資
- 採用活動
- 推し活
- 支払方法
- 改善活動
- 新規顧客
- 星のや
- 界隈消費
- 福利厚生
- 経営
- 自己効力感
- 自治体
- 行列
- 診断
- 講演
- 雇用創出
- 非日常
- 顧客体験
- 顧客満足
- 顧客理解
- 顧客調査
- 高NPS